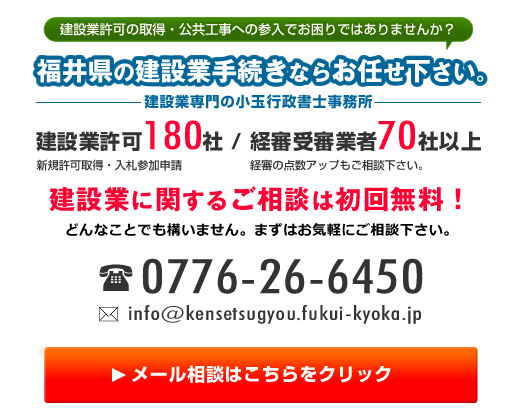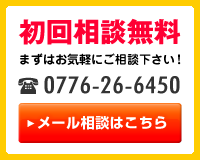令和7年3月31日をもって福井県証紙が廃止となったため、福井県への許認可申請手数料は「福井県手数料納付システム」で納める事になりました。
分かりにくいというお問い合わせを多数いただいておりますので、こちらでご説明させて頂きます。
納付方法は、下記の3パターンあります。
①直接、申請部署へ行き、クレジットカードや電子マネーで納める。(各窓口に決裁端末があります)※直接申請先へ行っても現金納付はできません。
②福井県電子納付システムを利用してクレジットカードで納める。 ※注※領収書が出ませんので、個人での立替時は事前に事業主にご確認下さい!
③福井県電子納付システムを利用してコンビニで納める。
②、③の場合の利用方法は以下の通りです。
福井県電子納付システム(建設業)はこちらからアクセスできます。
手数料の対象となる届出のリストが表示されていますので、その中から必要な項目を選び、必要項目を入力して申込を確定させます。
クレジットカード払いの場合は、そのまま決裁画面へ移ります。
コンビニ払いの場合は、そのままコンビニ払い申込画面へ移ります。
申込終了後、福井県から「納付申込完了のお知らせ(申込番号:2XXX-0001-XXXX)」というメールが来ますので、そのメールの申込番号を申込番号記入欄へ記入し、申請書類と一緒に提出します。
③の場合、コンビニのレシートは頂けますので、「領収書がある。」という意味で、こちらの方法が一番楽かもしれません。現在はセブンイレブンのみ、店舗での端末操作がなく、レジでスマートフォン画面にバーコードを表示させて支払うことができます。
***********************************************************************************
注意点は以下のとおりです。
①前述したようにカード払いでは領収書が発行されません。法人の場合、法人カード以外での決済時は事前に経理担当者に経費精算の方法について確認を取った方が良いでしょう。
②経営事項審査は今までは県証紙11,000円(1業種の場合)でしたが、これからは、(1)経営規模等評価手数料(10,400円~)、(2)総合評定値の通知手数料(600円~)の2つを申し込んで支払う必要があります。(金額は今までと同じです)
③建設業許可の場合、(1)建設業許可申請手数料(新規許可)90,000円、(2)建設業許可申請手数料(業種追加許可申請)50,000円、(3)建設業許可更新申請手数料50,000円の区分があります。ご自身がが申請する区分以外で手数料を支払うと手数料納付の確認が難しくなるとの事なのご注意ください。